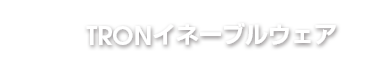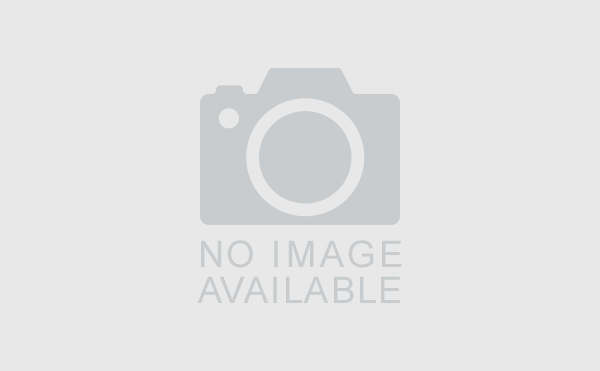TRONイネーブルウェアシンポジウム37th
最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー
2024年12月7日(土)13:30〜16:30(開場13:00)リアルとオンライン同時開催
INIADホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)
- 主 催
トロンフォーラム/TRONイネーブルウェア研究会 - 共 催
INIAD cHUB (東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)/東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター - 特別協賛
グーグル合同会社/大和ハウス工業株式会社/株式会社デジタルガレージ/日本電気株式会社/日本電信電話株式会社/パーソナルメディア株式会社/株式会社パスコ/明光電子株式会社/ユーシーテクノロジ株式会社/株式会社横須賀リサーチパーク - 協 力
矢崎総業株式会社
| 13:00 | 受付開始 |
| 13:30~14:00 | 基調講演「最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー」 坂村 健:東京大学名誉教授、TRONイネーブルウェア研究会会長 |
| 14:00~14:20 | 講演「災害時における情報通信インフラ対応と被災地の障害者支援」 田邊 光男:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長 |
| 14:20~14:40 | 講演「能登地震における情報バリアフリー確保に向けた取り組みと課題」 荒金 陽助:日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長 |
| 14:40~15:00 | 休憩 |
| 15:00~15:20 | 講演「障害者の避難を阻む『壁』」 竹内 哲哉: NHK 解説委員室 解説委員 |
| 15:20~16:30 | パネルセッション 田邊 光男、荒金 陽助、竹内 哲哉、坂村 健(コーディネータ) |
| 16:30 | 閉会 |
2024年の能登半島では、1月1日の地震と9月の大豪雨により大きな被害がもたらされました。2024年8月には初めて南海トラフ地震臨時情報が発表されました。また、近年日本では、地球温暖化の影響による局所的な集中豪雨も頻発しており、多様な自然災害や、さらにはその複合化への備えの重要性もますます高まっています。
災害発生の緊急時には、被害予想、避難警告、被害状況などの情報が多く出され、それに基づき適切な行動をとることが欠かせません。しかし障碍者は適切な情報伝達手段の確保に困難をきたすことがあります。また、災害からの復興期も含め、平時からの障碍者支援コミュニティの形成が求められています。
今年のTEPSでは、最新技術の力を活用した災害時の障碍者支援と、災害にも対応できるコミュニティづくりについて議論します。
講演概要
最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー
坂村 健
東京大学名誉教授
TRONイネーブルウェア研究会会長
近年、地震や豪雨による大規模災害が頻発する中、災害弱者と呼ばれる高齢者や障碍者の方々への情報提供は依然として大きな課題となっている。特に従来の画一的な情報発信では、視覚・聴覚障碍者や外国人居住者など、情報弱者への適切な情報伝達が困難であった。
しかし、昨今飛躍的な進歩を遂げている生成AI技術は、この課題を解決する大きな可能性を秘めている。例えば、災害情報を個々人の理解しやすい形に自動で変換したり、刻々と変化する状況を自然な言葉で説明したりすることが可能になる。視覚障碍者向けには、カメラやセンサーで得られた周辺状況を的確な言葉で説明し、聴覚障碍者に対しては音声情報をリアルタイムでテキスト化して伝えることができる。
さらに、発災直後の緊急情報提供に留まらず、避難所生活における様々な場面でも生成AIの活用が期待できる。例えば、個々の障碍の特性に応じた生活上のアドバイスを提供したり、周囲の人々に対して障碍者との適切な関わり方のヒントを示したりすることが可能だ。避難所という非日常的な環境下でこそ、AIによるきめ細かな情報支援が真価を発揮する。
生成AI技術の特徴は、単なる情報の変換や翻訳に留まらない、状況に応じた適切な情報の生成にある。例えば、避難所でのコミュニケーションにおいて、文化的背景の異なる外国人に対して適切な表現で情報を伝えたり、障碍の種類や程度、避難所の混雑状況や設備の状態といったコンテクストに応じて情報の粒度や提供方法を最適化したりすることができる。
本講演では、このような生成AI技術の可能性と、それを災害時の情報バリアフリーに活用するための具体的なアプローチを示したい。技術の進歩が切り拓く、すべての人が必要な情報に適切にアクセスできる社会の実現に向けた展望を描いていく。
災害時における情報通信インフラ対応と被災地の障害者支援
田邊 光男
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長
能登半島地震等においては、国民生活の重要なライフラインである情報通信インフラにも影響が大きく及び、通信回線の断線や停電等により通信サービスが利用できなくなる、テレビ・ラジオ放送が視聴できなくなる等の被害が発生しました。
そうした状況下においても、民間事業者や自治体、政府機関が連携し、通信・放送の早期復旧に向けた取組みを実施したほか、衛星通信サービスを始めとする新たな技術が活用されています。
能登半島地震での課題や教訓を踏まえた、情報通信インフラの強靱化に向けた今後の総務省の取組み等についてご紹介いたします。
また、災害・緊急時に際しては、正確かつ迅速に情報を得ること、そしてその情報を基に適切な判断を下し、周りの人々との効果的な意思疎通を行いながら、安全を確保する行動をとることが求められますが、特に、視覚や聴覚等に障害のある人々は、これらの状況下で格段に困難を経験します。
そこで、能登半島地震の際に総務省よりお知らせした、「令和6年度能登半島地震による被災地の障害当事者の方とその周囲の方へ」や「災害・緊急時における障害者等の利便増進に資するICT機器等の利活用推進ガイド」といった、障害者等の利便増進に資する総務省の取組み等についてご紹介いたします。
能登地震における情報バリアフリー確保に向けた取り組みと課題
荒金 陽助
日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長
今年1月の能登地震、ならびに9月の能登豪雨において、通信ネットワークは大きな被害を受けた。NTTグループでは通信設備の早期復旧に向けてあらゆる手段を講じるとともに、地域の皆様とも連携しながら災害支援の取り組みを行ったが、災害発生後、当該地域が一斉に情報バリアに阻まれた環境下においては、通信インフラ確保はこれまでにない困難を極める状況であり、情報バリアフリーの実現に向けた課題も浮き彫りになった。
一方、NTTでは、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想の2030年の実現に向けた研究開発を推進している。IOWN構想は光を中心とした革新的技術を活用し、これまでのインフラの限界を超えた高速大容量通信ならびに膨大な計算リソース等を提供可能な端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想である。さまざまな情報を組み合わせ、デジタルツイン上に高精度に再現し未来の予測ができるようになることから、災害予測や被災者支援の高度化が可能となるほか、分散コンピューティングにより被災時の迅速なリソース制御も可能となるなど、災害時の“バリアフリー”への貢献が期待されている。
今回は、能登地震の設備復旧に向けた取り組みや今後に向けた課題を振り返るとともに、IOWNが実現する災害時のバリアフリー実現に向けた取り組みを紹介する。
障害者の避難を阻む『壁』
竹内 哲哉
NHK 解説委員室 解説委員
毎年、発生する自然災害。気候変動もあり被害は甚大になる傾向があります。しかし、障害のある人たちが避難しようとすると、様々な「壁」が立ちはだかります。実際、障害者の死亡率は高く、東日本大震災のときに障害者手帳を持っている人々の死亡率は、住民全体の約2倍というデータもあります。
そして、その「壁」は障害のある一人一人、それぞれ違います。国は2013年に法律を改正し「避難行動要支援者名簿」の作成を自治体に義務づけ、名簿に基づき災害時の避難手順や避難所での対応をあらかじめ整理しておく「個別避難計画」の策定を市町村の努力義務としました。
ことし6月の総務省の調査によると「名簿」はすべての自治体で作成済みであるものの、「避難計画」についてはばらつきがあることが分かっており、計画に基づいた避難訓練も行われておらず、実効性については課題があります。
実際、ことしの元日に発生した能登半島地震では、発災当初、連絡がつかない障害者が数多くいたことが分かっています。
また能登半島地震では、様々な避難をするための「壁」(道路の寸断など)、避難所での「壁」(ライフラインの断絶、福祉の担い手不足など)も改めて浮き彫りになりました。
誰も取り残さず命を守るためにはどうすればよいのか。日頃からの障害者への理解や地域の連携のために必要なことを提起します。